アルコールと薬物との長い闘いーースタン・ゲッツ
村上春樹が訳した評伝『スタン・ゲッツ 音楽を生きる』を読みました。スタン・ゲッツ Stan Getz はジャズのテナーサックス奏者。村上氏が個人的に一番思い入れのあるミュージシャンなのだそうです。原著は1996年に出ていて、この邦訳が出たのは2019年です。20年ぐらいかけてポチポチと訳したんでしょうか。一見それほどの分量があるようには見えませんが、600ページぐらいあります。薄い紙を使っているんですね。
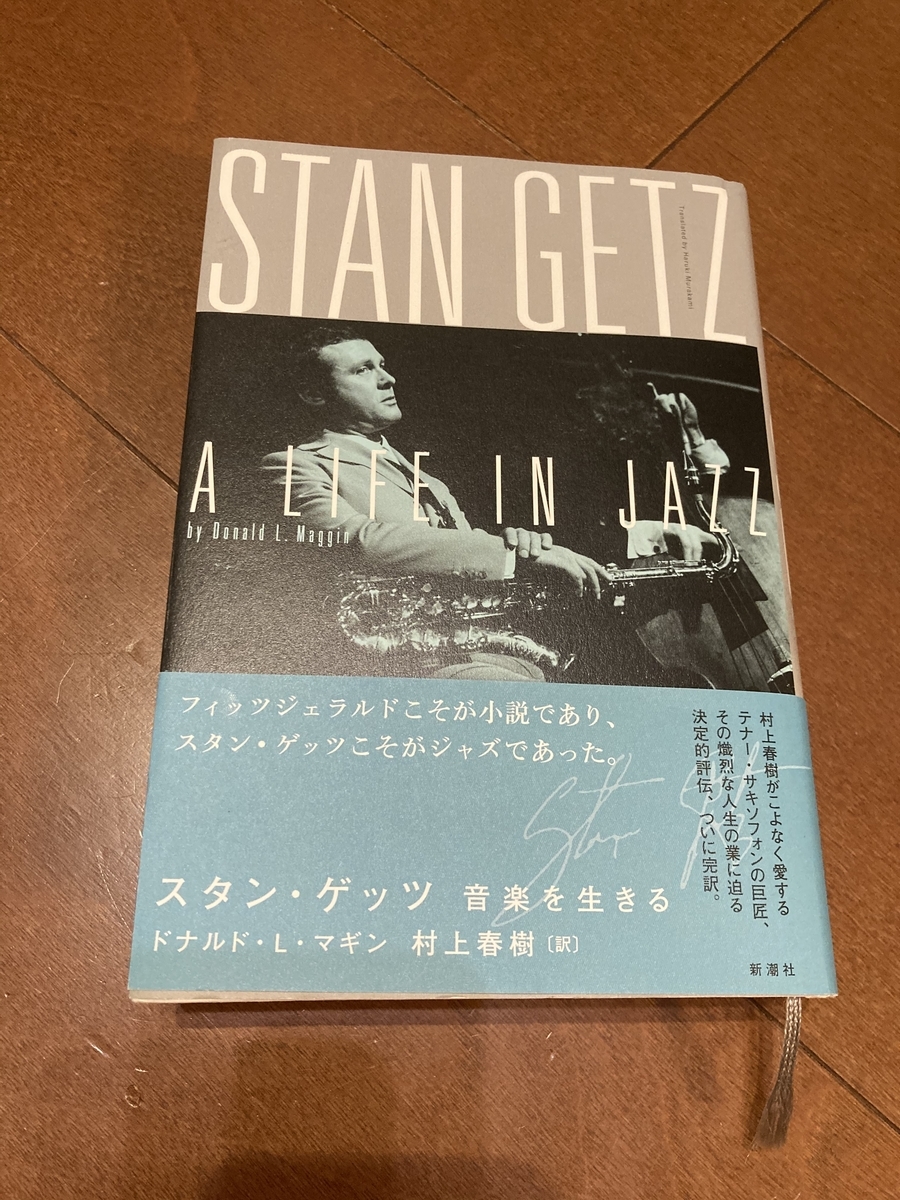
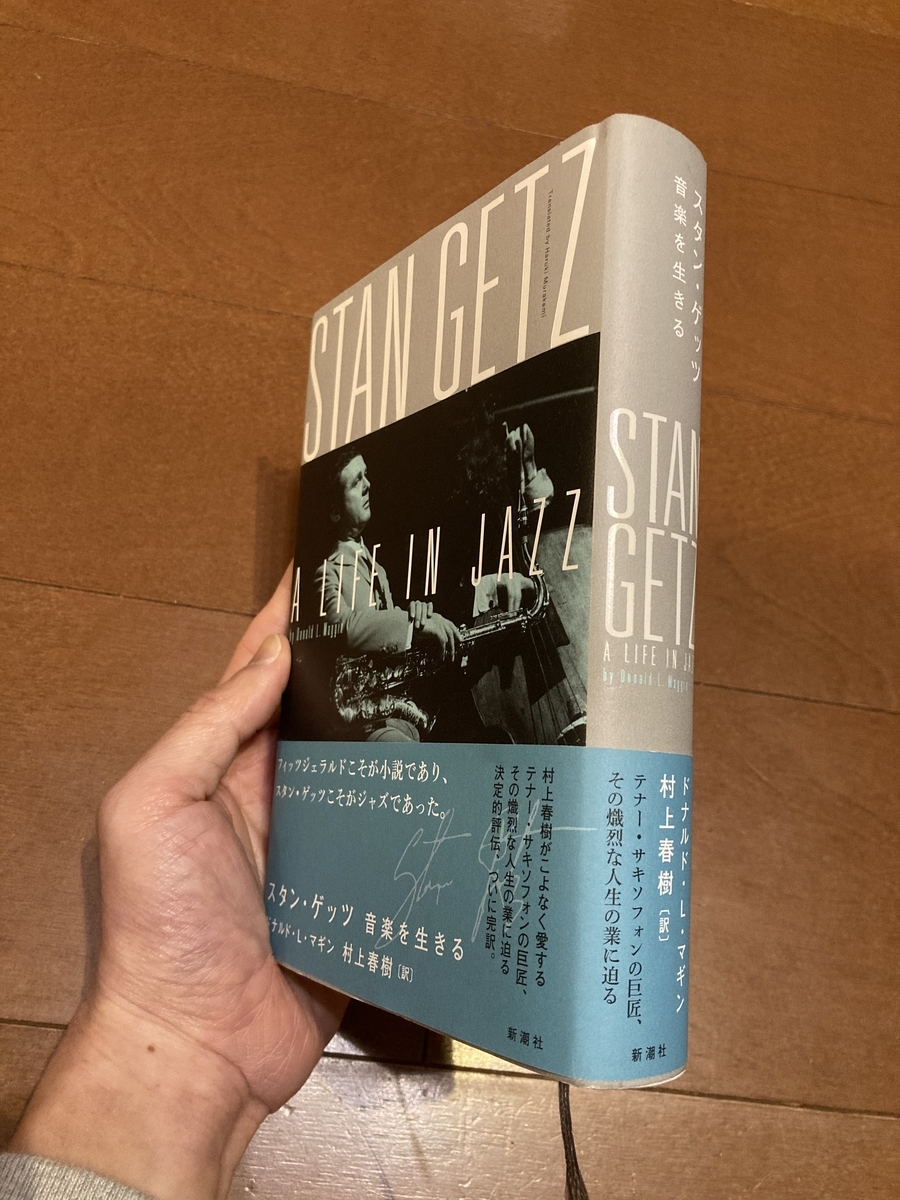
訳者あとがきにもありますが、スタン・ゲッツは人格に大きな問題を抱えていると見られることが多い人物でした。ジャズメンのエピソード集なんかでもいいことが書かれているのを見たことがありません。
ルイ・カストロ『ボサノヴァの歴史』に少しだけ登場するゲッツの姿は、ボサノヴァのデリカシーを理解しない尊大で無神経なアメリカ人そのものです。
渡辺貞夫の『ぼく自身のためのジャズ』では、日本公演とその後のレセプションについて触れられていますが、気合いの入ってない演奏だった上にレセプションの席で話すことといったらトルコ風呂がよかったとかいう、音楽と関係ない話ばかりで閉口した、という調子でした。
評論家・ジャズ喫茶経営者の寺島靖国なんか、ゲッツがドラッグストアでの強盗容疑でつかまったときのエピソードを紹介して、(ゲッツの音はソフトでふわふわしているが)このときばかりは颯爽としていたに違いない、なんてよくわからない書き方をしているし。
一番好意的といえるのは、ビル・クロウの『さよならバードランド』(同じく村上春樹訳)で引用されたズート・シムズによるゲッツ評でしょうね。
「うん、スタンというのはまったく感じの良い人たちだよ!」
多重人格的に感情の移り変わりが激しい人だったわけです。
その一方でゲッツの音色やフレージングは、ジョン・コルトレーンの「もしそうできるものなら、すべてのテナー奏者はスタン・ゲッツのように吹いていることだろう」という言葉に代表されるように、多くの人を魅了してきました。
一人の人間の中に多様な面が同居していることは、程度の差はあれ、だれにでも当てはまることだと思います。単純に「性格には問題があるが音楽性は素晴らしい」といった陳腐な言葉では片付けられない、複雑な過程の反映だといえるでしょう。この本ではその過程を丹念にたどっていきます。
僕自身はゲッツをそれほど熱心に聴いてきたわけではなく、At Storyville vol.1 & 2 というライヴ盤や Stan Getz Plays,Getz/Gilberto といった有名盤ぐらいしか知らなかったのですが、本書で紹介されている音源をサブスクリプション音楽サービスで探して聴きながら読みました。想像以上に幅広い音楽に取り組んだ人だということがわかりましたし、Focus のような前衛的な作品の制作もかなり主体的にかかわっていたことを知りました。音楽に関する探求心の強さは随所に現れます。
印象深いのは、スタン・ケントン楽団に在籍して初めてソロをとらせてもらった十代の頃、まだ全然退屈なソロだったというアニタ・オデイの証言。そこからあの流麗なフレーズを次々に繰り出すまでに成長するのですから、どれだけ研鑽を積んだのでしょう。音楽に真摯に向き合う姿勢は終生変わらなかったようです。
同時に生涯つきまとったのがアルコールとドラッグとの闘いです。十代の頃にまったく罪悪感なくヘロインに手を染め、薬物とアルコールはその後多くの問題を起こす原因となるわけで、そのあたりのところは読んでいてつらいものがあります。ジム・キャロルの『マンハッタン少年日記(原題をそのまま使った『バスケットボール・ダイアリーズ』として後にレオナルド・ディカプリオ主演で映画化)』を読んだときも同じ感想を持ちました。現代アメリカの深い病巣ですね。しかしゲッツは結局この闘いに打ち勝つのです! やはり非凡だと言わざるを得ません。
この本を読み、ゲッツの遺した音源に耳を傾けると、ジャズという音楽の素晴らしさを改めて感じることができると思います。そしてスタン・ゲッツという希有な人物のことも好きになるでしょう。